
昨年末から勃発したロックバンド・クイーンのブームが覚めやらない。かくいうぼくも、日々、仕事をしながら、時々ヘッドフォンの爆音で聴いている。
特にRadio Ga Gaという一曲が、実に、鮮明に、自分が今まで生きてきた中でのエポックを脳裏に蘇らせてくれる。
そう、そして、クイーンという当時あまりにも摩訶不思議なバンドを知ったのもラジオだった。
クイーンの曲ではじめて聴いたのはKiller Queen。確か中学2年頃だった。すべてのぼくロックの原点が太素塚裏の家の2階の部屋からはじまった
当時は、クラスを中心にした音楽、特にロックが好きな奴らが、太素塚(十和田市新渡戸記念館のある森)の裏のぼくの自宅の2階の部屋に、ほぼ毎日誰かがたむろしていた。
サッカー少年で新聞配達もする働き者のカワという友人が、また、自分の家の父親とソリが会わず、ほとんどぼくの部屋に泊まりに来ていた。その他の常連が、カズヤにコムラ、歯医者の息子キタムラ。キタムラの家には、ゴージャズなステレオセットがあるので、レコードを本格的に聞くには、キタムラの部屋にも集まったりした。
ともあれ、ある夜、
その番組はニッポン放送のオールナイトニッポンか、NHKのリクエストアワーかどちらかだろう。
ぼくたち音楽バカは、必ず毎日、その番組を聴いていたから確かにそうだろう。
Killer Queenをはじめて聴いたときの衝撃といったら、当時、殆ど時間を費やして聞いていたビートルズもぶっ飛んだ。
例えれば、ブルース・リーの「燃えよドラゴン」で、はじめての怪鳥音の雄叫びと、張り裂けるような肉体美と、高速を超えたスピードのパンチ、キック、体の動きを大きなスクリーンで見た、あの天地がひっくり返るようなカルチャーショックに近いものを、Killer Queenのメロディーと、フレディー・マーキュリーの女性のような声、そして、ブライアンメイの今まで聴いたことのない、バイオリンと琴が混じったような不思議なエレキギターの音、そして、ドラムスのロジャー・テイラー、ベースのジョン・ディーコンを含めたメンバー4人全員のクラシカルなコーラス。衝撃だった。
翌日、学校へ行き、いの一番に、もっともロック通だと信頼してたカワに、言った。
「カワ、クイーン、知ってらが?」
「昨日、聴いだ。スゲーな」
即座にぼくは、お年玉やらで貯め込んでいた小銭を集めて、シングルレコードの「キラークイーン」を買って、小さなおもちゃのようなモジュラーステレオで何度も、何度も聴いた。LPレコードも出ていたが、お金がないので、まだ買えなかった。
けれど、新聞配達で確実な小遣い収入を得ていたカワは、すぐさま「キラークイーン」が入ったサードアルバムと、当時まださほどヒットしていなかったファーストアルバム「戦慄の王女」とセカンドアルバム「クイーンⅡ」を買ってきた。羨ましかったが、カワは自分の家であまりレコードを聴かないので、ぼくの部屋で聴いたはずだ。(と思う)ともあれ、新しいクイーンの音源に一気に触れてしまったのである。
それから、ぼくらの音楽生活は、クイーンで全く違ったものになった。
だが、
ぼくらは、中学の音楽通の中ではマイナーな存在となった。
なぜなら、当時のロックは、ビートルズはややオールティーズな感じで、メインのカッチョイイロックといえば、ディープパープル、レッドツェッペリンを主体とした、ヘビーメタルロック(後のヘビメタ)だった。
男が男として、吼える声でロックし、ギターがベロンベロンとなり引き、汗臭い長髪の男たちが狂気のケダモノのように、ステージで動き回る。
が、クイーンときたら、長髪で女のようなフレディーが、あたかもサウンド・オブ・ミュージックのミュージカルのような声といでたちで、うう~う、と女よりも女くさい声で、美しいメロディーを叫んでいる。
さらに、
ぼくら中学生のさ迷えるクイーンファンに、決定的な自信を与えたのが、
4枚目のアルバムである「オペラ座の夜」だった。
そして、その中で、その後のロック界というよりは、ポピュラーミュージックにとんでもない大きな革新を起こした作品が、
「ボヘミアン・ラプソディー」だった。
ともあれ、時は過ぎ、
なぜか、ぼくは、山形県の天童という将棋で有名な町の映画館で、
「ボヘミアン・ラプソディー」というタイトルの映画を見た。
そして、昨日、東京・市ヶ谷で行われる故郷十和田市の同郷の集い「東京十和田会」に行く途中の電車で、スマホのヘッドフォンを大音量にして、80年代の忘れていたクイーンの名曲を聴いていた。
Radio Ga Ga
この曲が流行ったとき、ぼくはモダンジャズに狂っていて、もはやテクノミュージックのようにしか聴こえなくなってしまったクイーンから遠ざかっていた。
当時のポピュラーミュージックの音は、シンセサイザー、コンピュータミュージックが一気呵成に流布する頃で、広告代理店勤めの中で、ポップな完成を求められながら、ドン臭い企画やコピーや喋りしかできない、自分を肯定するためなのか、あえて、古いモダンで、アコースィックな生音のジャズにこだわっていた。立川談志を筆頭として、超頑固な古典落語にも入り込んでいた。
そして、クイーンは、もはやダンスミュージックに過ぎないくらい、ポップすぎるバンドになっちまったと思っていた。
ところが、
Radio Ga Ga
そう、この曲は、ぼくがはじめてクイーンの音に出合った、太素塚裏の暗闇の中のラジオの音を、その当時、感謝と愛情をたっぷりに、
あたかもラジオが幼馴染の親友のように、恋人のように、好き、好き、LOVE LOVEと叫んでいるのをあらためて、思い知り、五臓六腑に沁み込ませた。
連休のちょっとばかり余裕のある、
中央線の電車の席で、一人ヘッドフォンで聴く、Radio Ga Gaに泣けた。
オレはこれから、故郷十和田の人たちに逢いに行くときに、こんなことに気づくなんて。
沁みた。
そして、20代半ば、広告業界に入る手前、舞台関連に憧れていたことを思い出した。
できれば、物語を書いたり、舞台と作ったりして飯が食えれば、などと思っていた20代。
その頃、最も影響を受けた作家で、俳優で、文筆家、サム・シェパードの一冊の本を、今も大切に、時々読み返している。
その後、ぼくはヘタクソな戯曲を書き、その一本の中に、彼の作品から「ラジオの国から来た男」というキャラクターを作り上げた。
その影響をくれた、サム・シェパードのエッセイの一説を、これを読んでくれているキミに届けたい。
ラジオが「友だち」
だというギタリストを知っていた。彼は音楽よりも、ラジオの声によほど親しみを覚えるのだ。その声の、なにか人工的な質。ラジオを通して聞こえてくる声ではない。ラジオの声そのものだ。遠くにいる人々がすぐ近くで喋っているように錯覚させるラジオの力だ。彼はラジオと一緒に寝た。ラジオに話しかけた。ラジオに口答えした。彼は遠くの方にラジオの国があると信じていた。それはいくら捜し求めても見つからない国で、だから彼はその国から送られてくる声に耳を傾けるしかないのだという。彼はラジオの国から追放された身であり、それ以来、永久に電波を手探りし続けなければならない放浪の宿命なのだ--彼を失われた故郷に連れ戻してくれる魔法のチャンネルを、いつか奇蹟的にさぐり当てる日を夢見ながら。 ホームステッド・ヴァレー、カリフォルニア
79/12/22
サム・シェパード 『モーテル・クロニクルズ』 (訳 畑中佳樹、ちくま文庫)
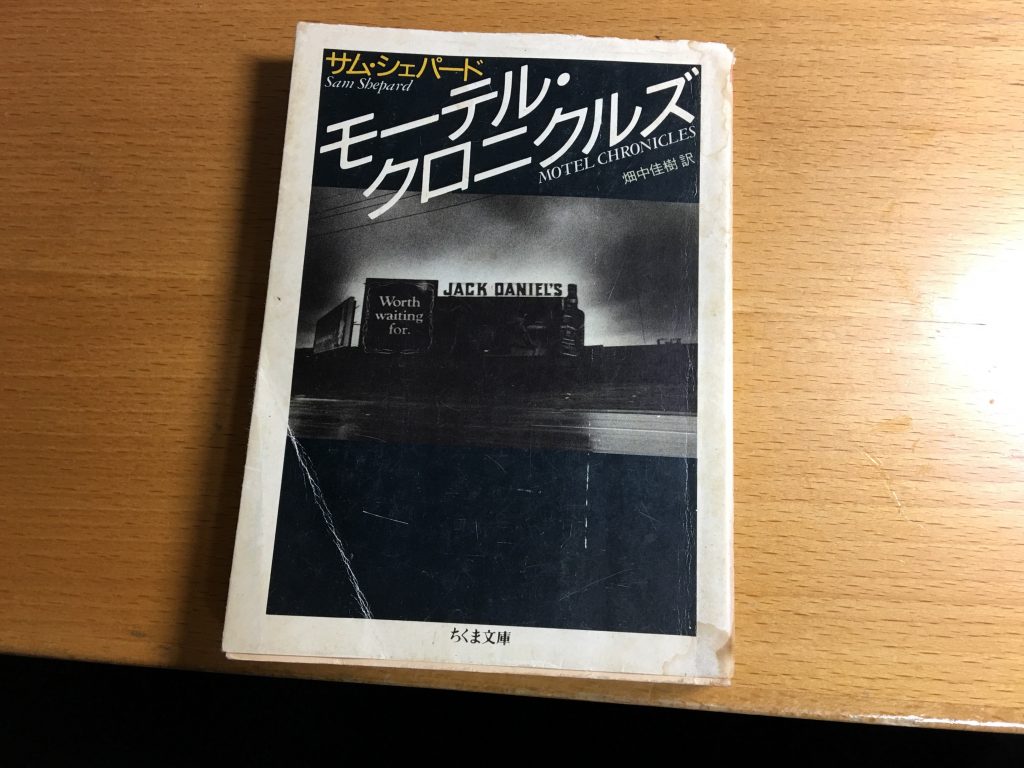
深読みしてくれれば、わかるかもしれない。
ぼくが、故郷 青森県十和田市の太素塚を愛し、新渡戸稲造の想いを愛せる理由がここにある。
もし、わかってくれるならば、
キミも、ラジオの国から追放され、魔法のチャンネルを探している身の上 なのかもね
Radio Ga Ga 日本語訳に感謝です!
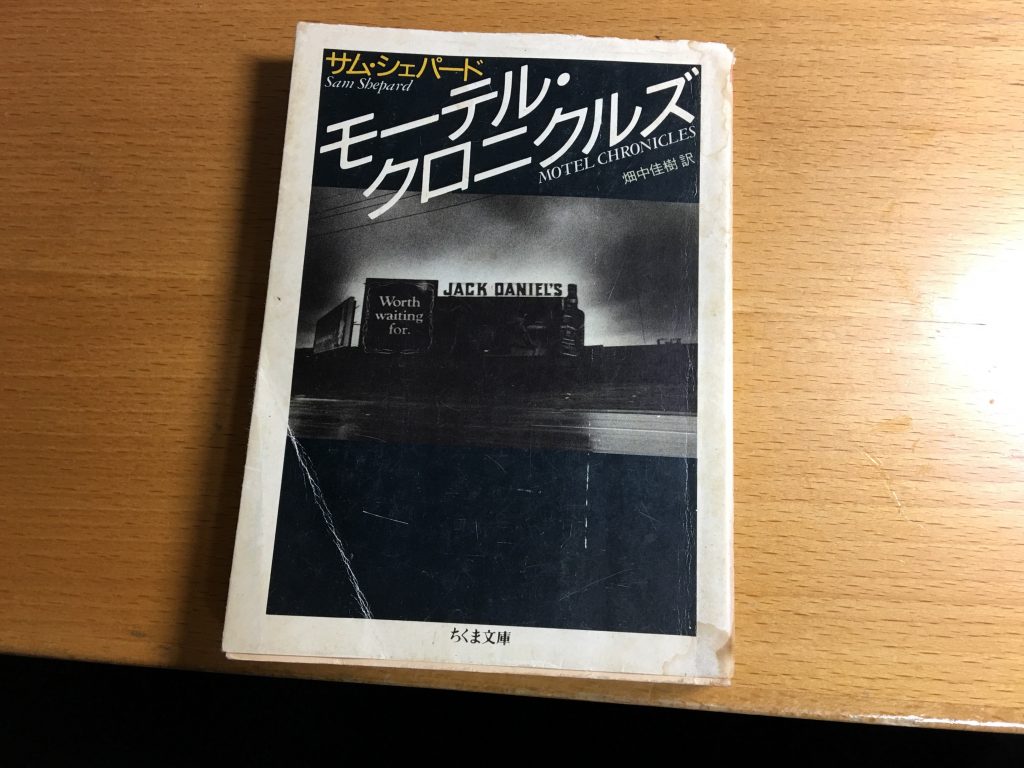






コメント